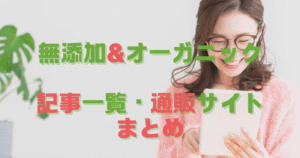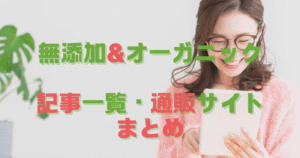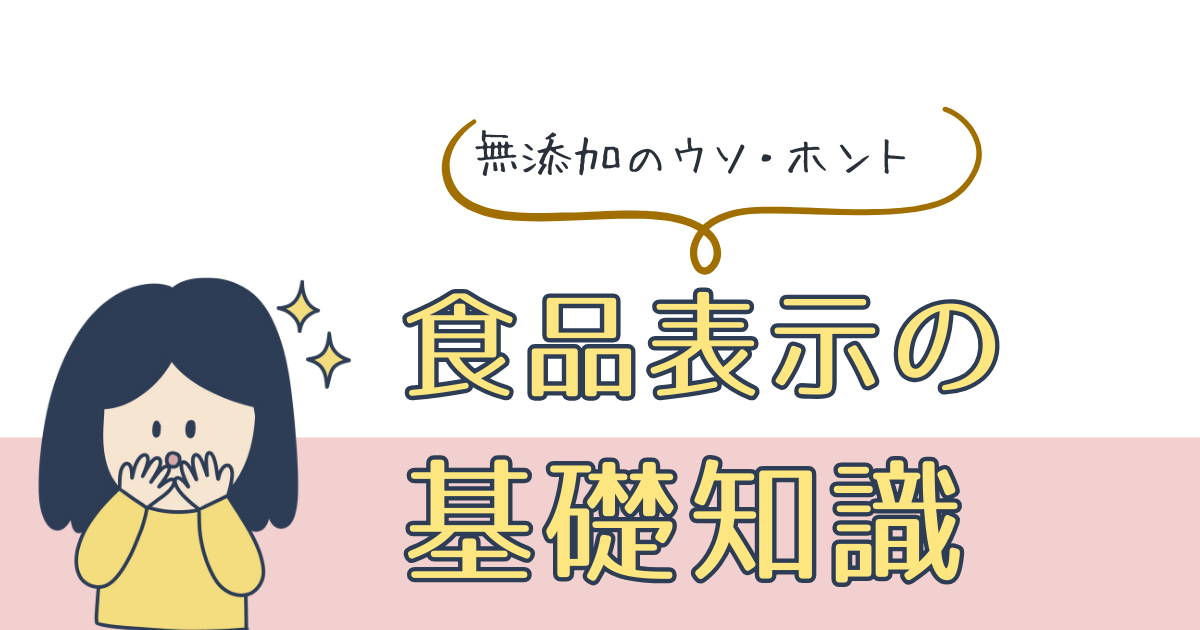くまここちゃん
くまここちゃん添加物表示のルールが知りたい!
そんな悩みにお答えします。
食品を選ぶときには、必ず原材料や添加物をチェックする!といった方は多いかもしれません。
しかし食品表示は複雑でわかりにくく、なるべくカラダとって良いものを選びたいと思っていても、正しい選択ができているか不安もありますよね。
でも最低限の知識を理解していれば、普段から頑張らなくても添加物の少ない食品選びや、安全性が懸念されている成分を避けることが可能です。
そこでこの記事では、私たちの身近にある「食品添加物」についての基礎知識や表示のルールについて解説。気になる「加工助剤」や、「キャリーオーバー」などの省略できるケースについても説明します。
この記事を読めば、添加物についての理解が深まり、食品選びにおいて必要以上に恐れたり、迷うことがなくなります。


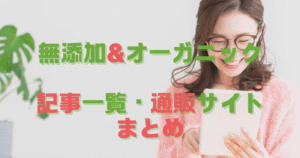
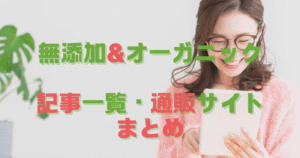
食品添加物とは?


食品添加物は食品衛生法・第4条において、
「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。」と定められています。
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
引用:厚生労働省>食品添加物
さらに添加物は、厚生労働大臣の指定を受けた「指定添加物」と、長年使用されてきた実績のある「既存添加物(天然添加物)」、さらに「天然香料」、「一般飲食物添加物」の4つに分類されています。
日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して厚生労働大臣が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されています。
引用:食品添加物とは?
食品添加物といえば、保存料や化学調味料など、なんとなくカラダに悪そうな成分をイメージされる方も多いかもしれませんが、
ラーメンに使われる「かんすい」など、古くから使われてきた成分も食品添加物として扱われるものがあります。
また逆に、「たんぱく加水分解物」や、「果糖ぶどう糖液糖」などのように、食品とは認識しにくいものでも添加物として指定されていない成分もあります。
そのため「添加物」だからといって全てを避けるべきとも言い切れません。
しかし個々の添加物の安全性や、省略される表示ルールによって誤解を招きやすいのが現状です。
なにが問題なの?


食品添加物は、厚生労働省や食品安全委員会によってリスク管理・評価が行われ、安全性が確認されたものが指定され使用基準が決められます。
食品添加物の安全性評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が行います(食品健康影響評価)。具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)が設定されます。
引用:Q3.食品添加物は食べても安全なのですか?
しかしその安全性評価は、それぞれ単体での動物実験が中心で、もちろんのこと、人間での長期的な試験はできません。
食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全性評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。
引用:食品添加物の使用基準と成分規格
また通常一つの加工食品を食べれば、同時に様々な添加物を摂取することになりますが、
この複合的な摂取についても証明がされていないので、単体での「一日摂取許容量」(ADI)を守っていたとしても安全性は確実ではない、、、といった点が懸念される理由のひとつです。
実際に一度認可された添加物が、取り消しになるといったケースは多々あり、
例えば、甘味料であるズルチンやチクロは一度認可されていましたが、現在では使用禁止になっています。
しかし同じように化学合成された甘味料であるサッカリンやアスパルテームなどはいまだ使用は認められていて、今後どうなるかはわかりません。
また次に解説する表示が免除されるケースもあるため、すべての添加物が原材料欄に記載されているわけでもないのです。
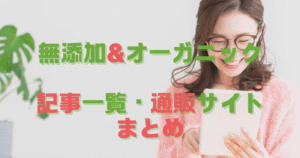
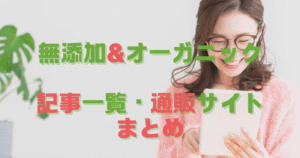
表示ルールと免除されるケース


食品添加物は、商品の「添加物欄」又は「原材料名欄」に、割合の高いものから順に記載されていて、
原材料名欄に書かれている場合は、スラッシュ「/」で区切ったり改行されていて、食品と区別されています。
添加物は原則として物質名を表示し、とくに消費者の関心が高い8種類については、使用目的や効果を表示することが義務付けられています。
(表示例)
用途名 用途目的 表示例 1 甘味料 甘味料 甘味料(ステビア)
甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物)2 着色料※1 着色料 着色料(赤2)
着色料(赤102、カカオ)3 保存料 保存料 保存料(安息香酸)
保存料(ソルビン酸)4 増粘剤※2
安定剤
ゲル化剤
糊料※2主として
・増粘の目的で使用される場合:増粘剤又は糊料
・安定の目的で使用される場合:安定剤又は糊料
・ゲル化の目的で使用される場合:ゲル化剤又は糊料増粘剤(アラビアガム)
安定剤(CMC)
ゲル化剤(ペクチン)
糊 料(加工デンプン)5 酸化防止剤 酸化防止剤 酸化防止剤(エリソルビン酸)
酸化防止剤(BHT)6 発色剤 発色剤 発色剤(亜硝酸ナトリウム) 7 漂白剤 漂白剤 漂白剤(二酸化硫黄) 8 防かび剤
防ばい剤防かび剤又は防ばい剤 防かび剤(イマザリル)
防ばい剤(TBZ)※1 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合、「着色料」の用途名を省略することができます。
引用:②用途名表示
※2 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合、「増粘剤」又は「糊料」の用途名を省略することができます。
しかし逆に表示を免除されるケースもあり、使用されている添加物がすべて記載されているとは限りません。



表示義務がないのは以下のパターンです。
一括表示


食品添加物のなかで、同じような用途である場合は一括表示が許されています。
例えば、パンやお菓子の製造に使われるイーストフードは、塩化アンモニウムや酸化カルシウムなどの10種類以上の成分が認可されている合成添加物であり、
そのなかの、どの物質がいくつ使われていても「イーストフード」のみ表示すれば良いことになっています。



一括表示ができる添加物は以下の通りです。
| 一括表示名 | 使用目的 |
|---|---|
| イーストフード | イースト菌の働きを強める |
| かんすい | 中華麺などの弾力、色、風味 |
| 酵素 | お茶の濁りをとるなど |
| 光沢剤 | 菓子などのコーティング |
| 香料 | 香りをつける、強化する |
| 酸味料 | 酸味をつける |
| ガムベース | チューインガムの素材 |
| 軟化剤 | チューインガムの軟らかさを保つ |
| 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、調味料(核酸)、調味料(核酸等)、調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)、調味料(無機塩)、調味料(無機塩等) | うまみ、味付け、味の強化、調整 |
| 豆腐用凝固剤(凝固剤) | 豆乳を固めて豆腐にする |
| 苦味料 | 苦味をつける、苦味を強くする |
| 乳化剤 | 乳化、消泡、品質改良など |
| 水素イオン濃度調整剤(pH調整剤 ) | 食品のpHを調整し、変色・変質を抑える |
| 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉 | ガスを発生させ、クッキーなどの生地を膨らませる |
例えば、スナックお菓子の添加物欄に、「調味料、光沢剤、香料」と書かれていたら、
それだけで何十種類もの添加物を一度に摂取している可能性があるということです。
食品添加物の表示は食品表示法で、「原則としてすべての食品添加物を『物質名』で食品に表示する」ように定められていますが、一部の食品添加物については使用目的を表す『一括名』で表示できる例外が認められており、物質名が表示されない食品添加物があります。
引用:物質名が表示されない食品添加物がある?
・参考URL:食品衛生の窓>一般用加工食品(添加物)




キャリーオーバー


キャリーオーバーは、原材料からそのまま持ち越される添加物のことで、残留して残っている可能性があっても添加物として記載されません。
食品の原材料に使用された添加物について、次のすべての条件に当てはまる場合は「キャリーオーバー」となり、表示が免除されます。
- 1.食品の原材料の製造又は加工の過程において使用されるもの
- 2.当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの
- 3.当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの
(例)
引用:一般用加工食品(添加物)
- ビール製造の際に使用されるスターチやホップ中の二酸化硫黄
- 揚げパンやドーナッツの製造に使用する揚げ油に含まれていた消泡剤としてのシリコーン樹脂
- シュークリームの原料配合中、少量使用されているマーガリンに含まれていた乳化剤
かんたんに言えば、原材料の原材料に含まれる添加物は、表示が免除されるケースがあるということ。
例えば「せんべい」の味付けに、保存料が含まれる醤油を用いたとしても、最終食品のせんべいに保存料としての効果を持たない場合はキャリーオーバーに該当します。
つまりカップ麺・レトルト食品・スーパーの惣菜などのように、多くの食品が混ぜられるものであればあるほど、隠れている添加物があるということです。


加工助剤


食品の製造過程で添加されていても、完成前に除去されたり中和されたりするものは加工助剤となり、表示が省略されます。
食品の加工の際に添加されるもので、次の3つのいずれかに該当する場合は「加工助剤」となり、表示が免除されます。
引用:一般用加工食品(添加物)
- 1.当該食品の完成前に除去されるもの
(例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン- 2.当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
(例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム- 3.当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
(例)豆腐の製造工程中において、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂
例えば、食用油 や 脱脂加工大豆の製造時に使われるヘキサンは、
最終食品には残らないとされていますが、これはガゾリンに含まれる化学物質です。
これ以外にもアミノ酸液入り醤油に使われる塩酸や、カット野菜の洗浄・殺菌に使われる亜塩素酸ナトリウムも加工助剤に当たります。
☆亜塩素酸ナトリウム
酸性溶液中で生じる酸素による酸化作用で漂白します。漂白剤としての使用の他に、カット野菜等の生食用野菜や卵殻の殺菌の目的でも使用されます。最終製品の完成までに分解又は除去されなければならないとされています。
使用対象食品:生食用野菜類、卵類、ふき、もも、かんきつ類、果皮(製菓用)、さくらんぼ
引用:7 漂白剤




・参考URL:日本食品添加物協会>食品添加物の表示
栄養強化剤


使用した添加物のうち、栄養強化の目的で使用する一部の成分については、表示を省略できるケースがあります。
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲については、食品表示基準について(別添 添加物)に記載されています。
引用:食品衛生の窓>一般用加工食品(添加物)
なお、調製粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示が必要です。また、別表第4で表示義務のあるものは、栄養強化の目的であっても表示が必要となります。
具体的には、L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなどの「ビタミン類」、
亜鉛塩類、塩化カルシウム、塩化第二鉄などの「ミネラル類」。さらにL-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニン、L-イソロイシンなどの「アミノ酸類」です。
しかし実際には、L-アスコルビン酸は酸化防止剤として、β-カロテンは着色料としてなど、
別の目的にも使える添加物もあるため、どういった場合でも表示するべきではないかという意見もあります。
なお、同じ食品添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は、表示する必要があります。(例:酸化防止剤としてL-アスコルビン酸(ビタミンC)を使用する場合は、「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示する必要があります)
引用:国民生活センター>物質名が表示されない食品添加物がある?


・参考URL:食品衛生の窓>用途別 主な食品添加物
その他:表示面積が小さい、ばら売り等


加工食品の容器または包装の表示可能面積が小さい場合は、原材料の表示を省略できることになっています。
食品には、製造者の連絡先など表示すべきことがいろいろと決められていますが、表示のスペースが限られた食品では、全てを記載することが困難な場合があります。そこで、表示面積が小さい場合には、原材料の表示を省略することが認められています。表示の可能な面積が30平方センチメートル以下の場合が、食品表示法における省略の基準に該当します。
引用:Q8 小さい商品では、表示をしなくても良いと聞きましたが、本当ですか?
さらに量り売りや、ばら売りなど、あらかじめ容器包装のない状態で販売されるものに関しても、表示の義務はありません。
容器包装に入れず、ばら売りなどで販売される食品については、添加物を含む旨の表示義務はありません。しかし、次の場合は、売り場等に添加物の物質名及び用途名を使用した旨を表示することが望まれます(食品表示基準について(別添 添加物))。
引用:食品衛生の窓>その他の表示事項
- 1.防かび剤又は防ばい剤として、アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、ジフェノコナゾール、チアベンダゾール、ピリメタニル、フルジオキソニル又はびプロピコナゾールを使用した食品
- 2.甘味料のサッカリン、サッカリンカルシウム又はサッカリンナトリウムを使用した食品
・参考URL:表示レイアウト及び文字の大きさについて(平成26年3月20日消費者庁食品表示企画課)
まとめ:加工度の高い食品に注意


食品添加物の基礎知識や表示のルールについて解説しました。
添加物には一括表示のように、複数の種類がまとめて表示されているケースや、キャリーオーバーのように加工食品ほとに省略されている場合があり、
原材料名欄に書かれている以上に多くの添加物が使われている可能性があります。
そのリスクについては確実に安全であるとも言い切れず、私たちは自主的に添加物を減らす努力が必要です。
コンビニ弁当やスーパーの惣菜、お菓子やレトルト食品などの加工度の高い食品は控えめに、なるべく自然派の食品や、自炊を心がけるようにしましょう。